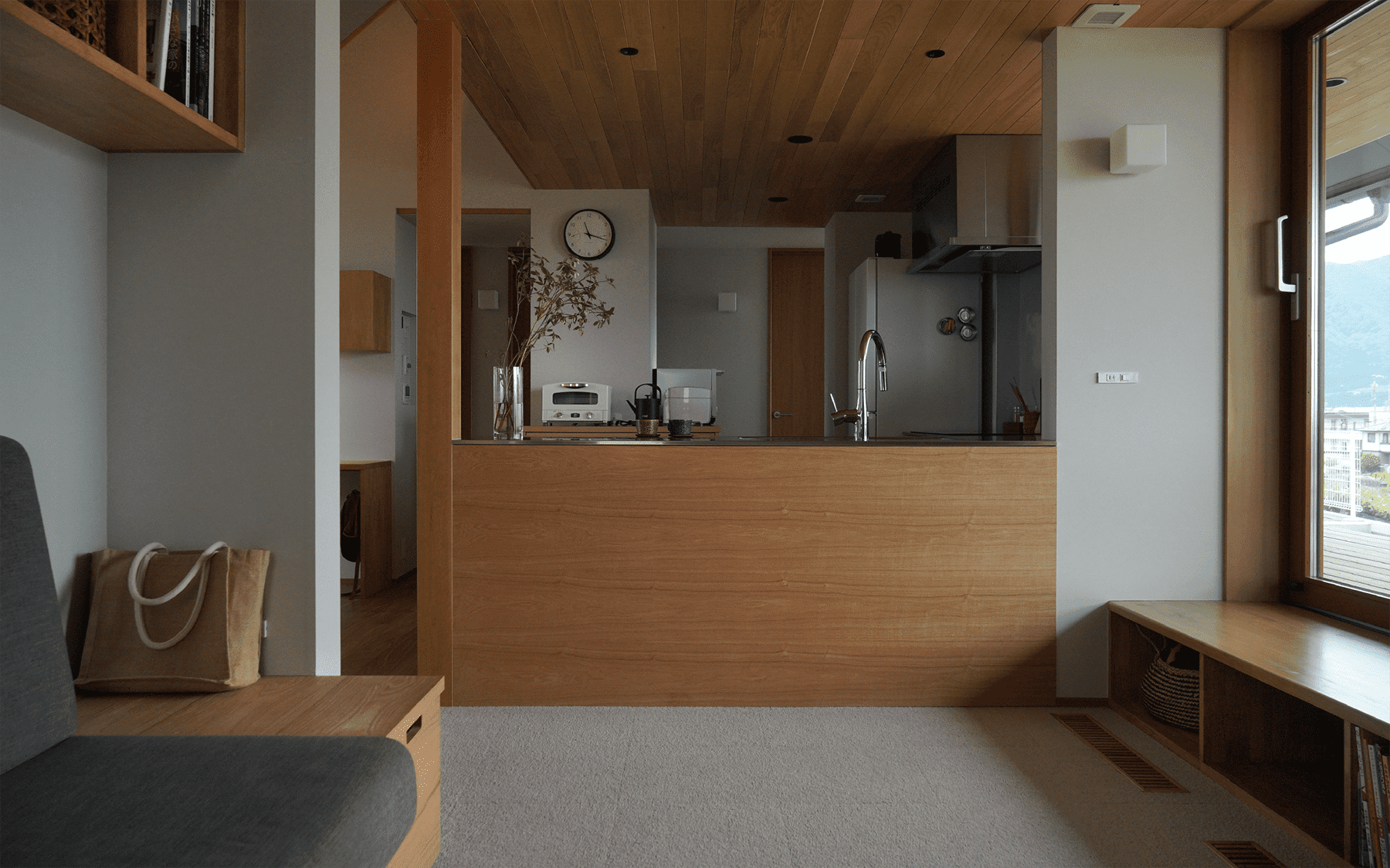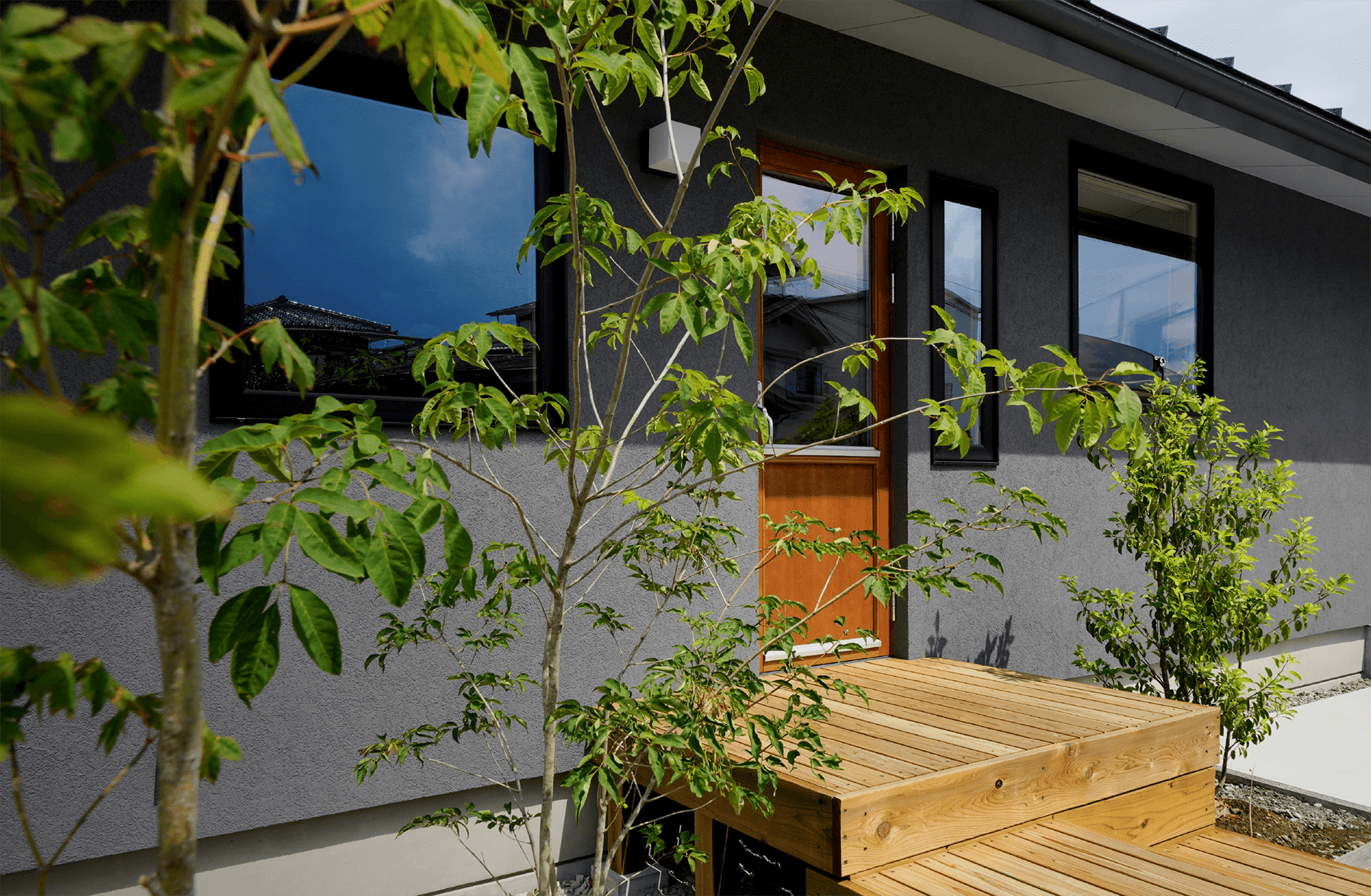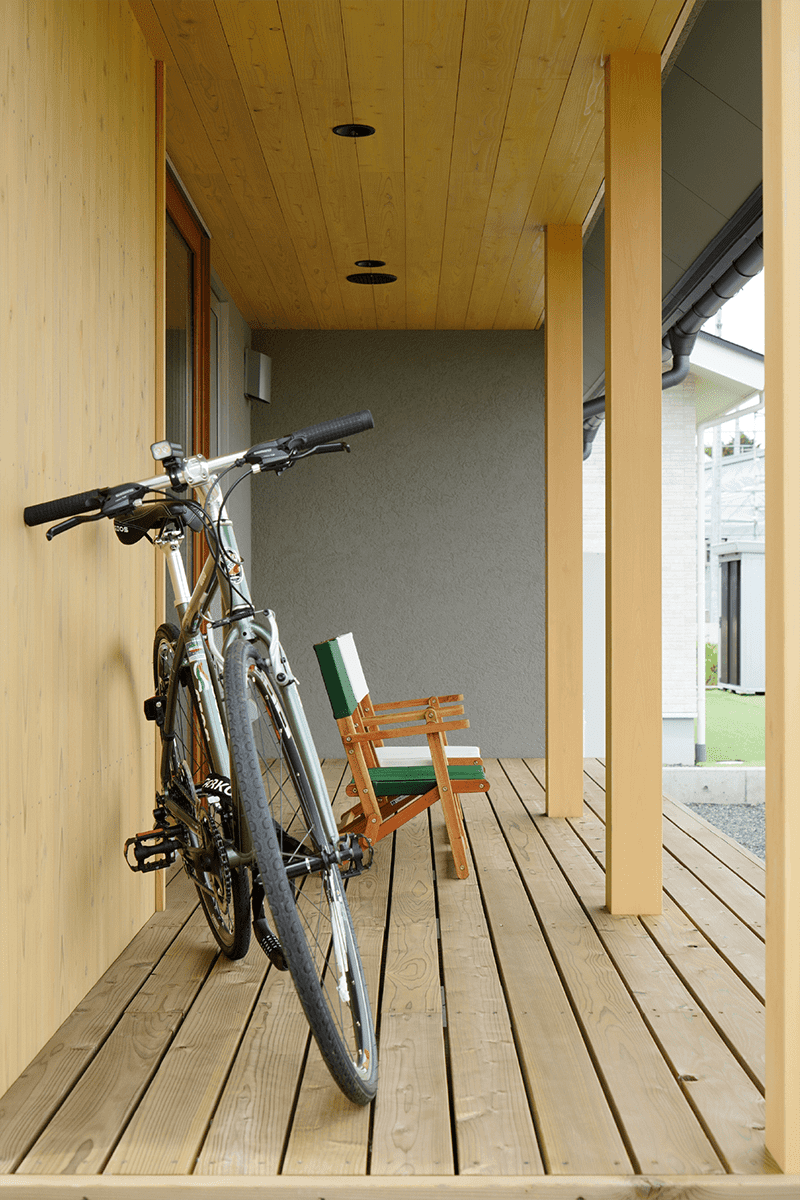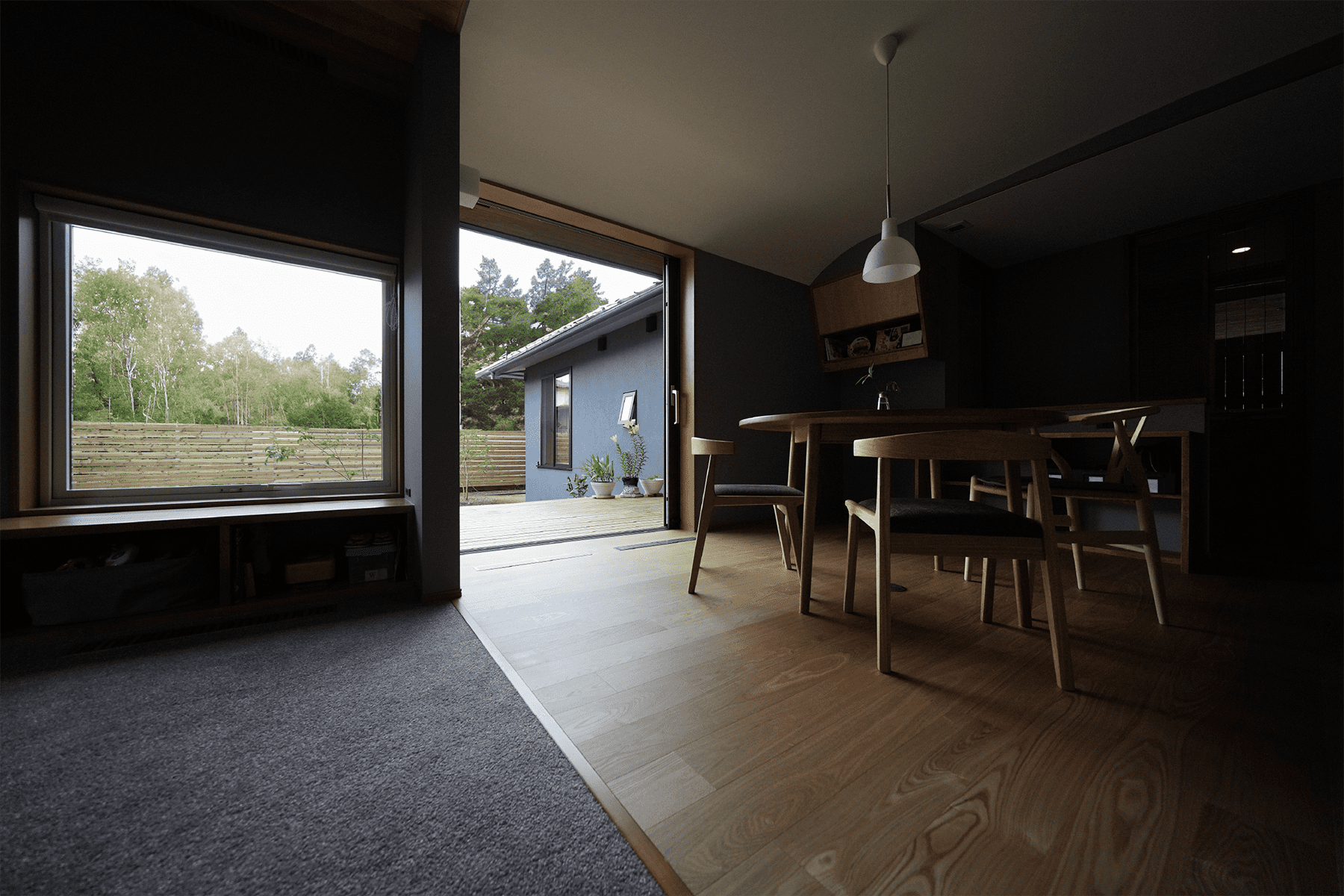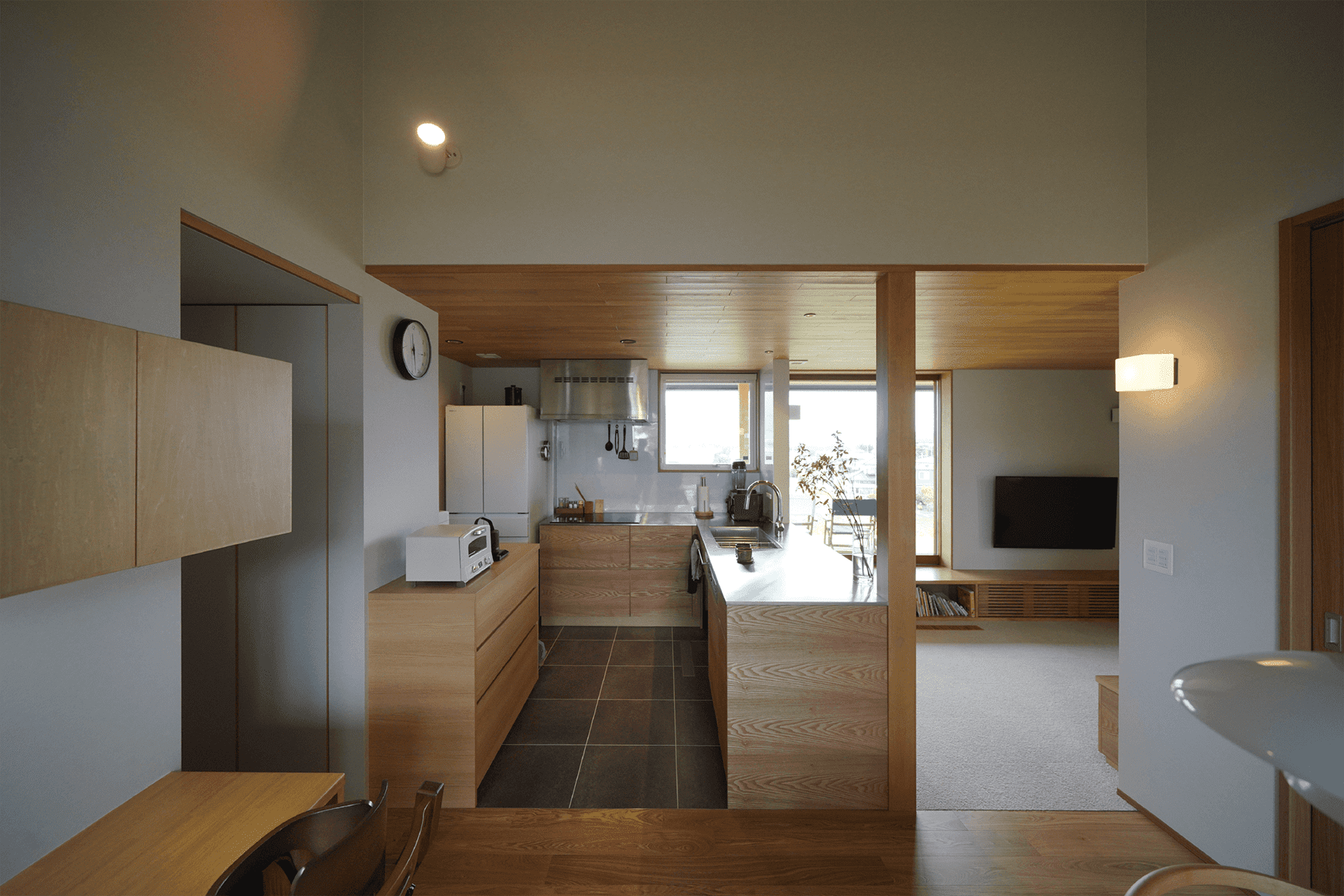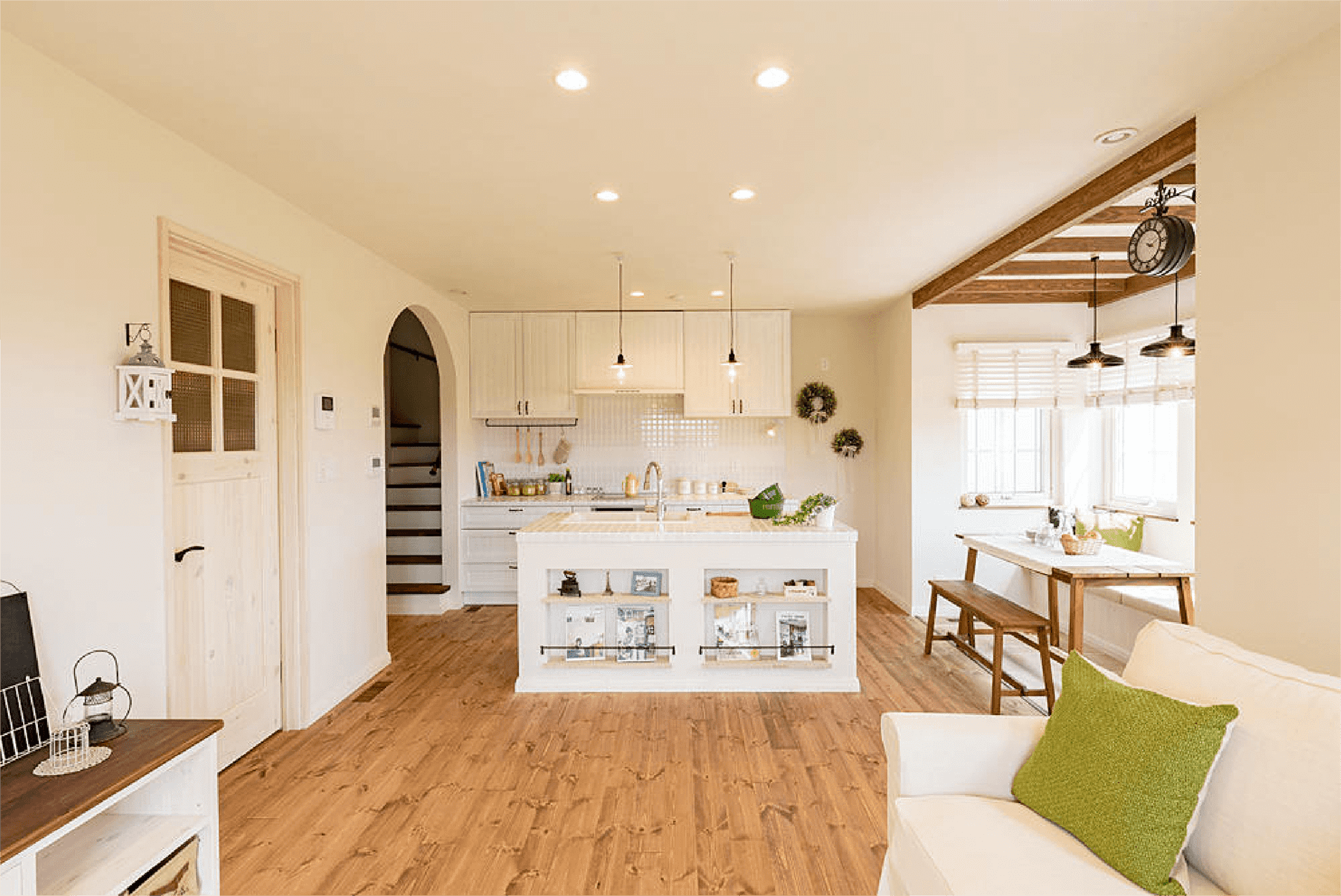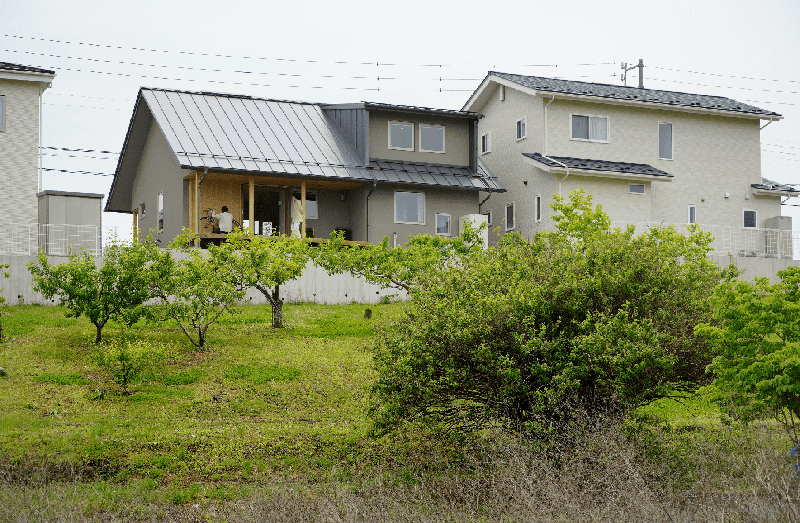KIをつかさどる家Harmonious Home
scroll
NEWS
LINE UP
FREE DESIGN
何気ない日々もしつらえる
提案型自由設計の家
VIEW MORE
PRODUCT HOUSE
自然素材のやさしい
プロダクトハウス“Skogのいえ”
VIEW MORE
WORKS
OWNER'S VOICE
オーナー様の
暮らし
FLOW 家づくりの流れ
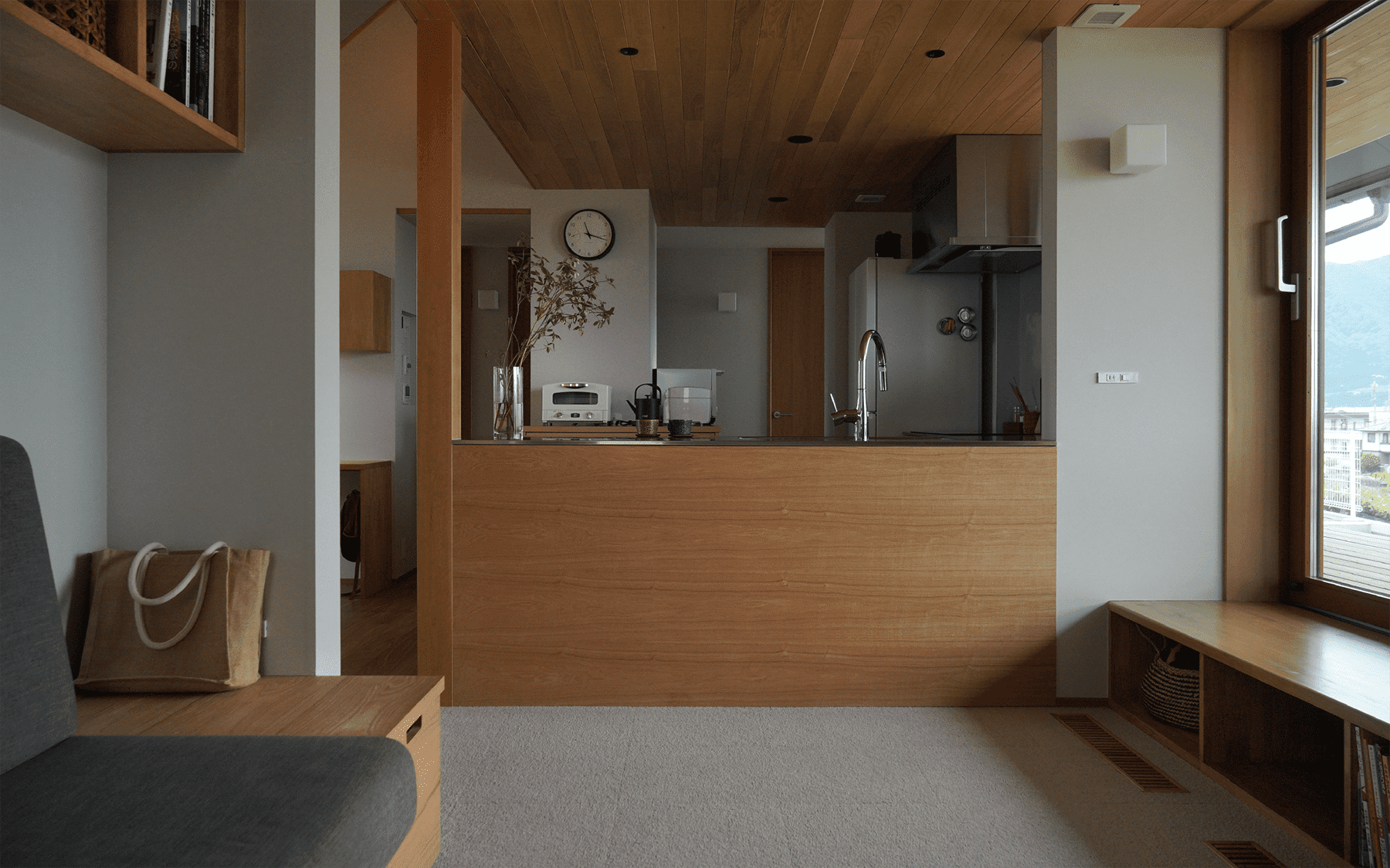
FLOW 家づくりの流れ